障害児施設の人員配置についての出題はあまり多くはないです。

しかし、「障害児入所施設」と「発達支援センター」、「医療型」と「福祉型」、違いが分かりづらいのが障害児施設・・・それぞれの施設の役割とともに、どのような職員が配置されるのか確認しておきましょう。
※「児童福祉法改正」により2024年4月より、「児童発達支援センター」が一元化され、医療型・福祉型の区別がなくなりました。
障害児施設の配置基準
障害児施設は次の3つ
- 医療型障害児入所施設
- 福祉型障害児入所施設
- 児童発達支援センター
「障害児入所施設」は入所型。発達支援センターは通所型で、地域の障害児やその家族への支援も行います。
「医療型」と「福祉型」の違いですが、「医学的治療が必要」な子が行くのが「医療型」です。
- 福祉型→福祉サービス
- 医療型→福祉サービス&治療
医療型の子の方が、重い障害を持っていると考えられます。
「医療型」「福祉型」の違いは?
分かりにくいのが、「自閉症児だからこの施設」「重症心身障害児だからこの施設」というのではなく、医療型障害児入所施設に入る重症心身障害児の子もいれば、福祉型児童発達支援センターへ通う重症心身障害児の子もいるということ。
障害別に施設が決まるのではなく、障害の程度や必要な支援などによって施設が決まるのです。
というのも、以前は、知的障害児通園施設、難聴児通園施設、重症心身障害児通園施設、自閉症児施設、ろうあ児施設など、障害別に施設が分かれていました。
それが、児童福祉法の改正により、平成24年度に再編され、通いやすくなったり、複数の障害を持つ子の治療や訓練がしやすくなったのです。
障害児入所施設
医療型と福祉型がありますが、児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者は共通です。
医療型☆☆
対象:
- 知的障害児
- 自閉症児
- 肢体不自由児のうち医学的治療の必要な障害児
- 重症心身障害児
支援の内容
- 疾病の治療・看護
- 日常生活能力の維持・向上のための訓練
- コミュニケーションの支援
- 医学的管理に基づく食事・排せつ・入浴などの介護
など
主として自閉症児を入所させる施設
- 医療法に規定する病院として必要な職員(医師・看護師など)
- 児童指導員および保育士(児童6.7人に1人)
- 児童発達支援管理責任者
肢体不自由児を入所させる施設
- 理学療法士または作業療法士
- 医療法に規定する病院として必要な職員(医師・看護師など)
- 児童指導員および保育士(乳幼児10人に1人以上、少年20人に1人以上)
- 児童発達支援管理責任者
重症心身障害児を入所させる施設
- 理学療法士または作業療法士
- 心理指導を担当する職員
- 医療法に規定する病院として必要な職員(医師・看護師など)
- 児童指導員(1人以上)
- 保育士(1人以上)
- 児童発達支援管理責任者
重症心身障害児は、重度の肢体不自由・重度の知的障害を持ち、ほとんどすべての日常生活動作について、全面介助が必要です。
保育士・児童指導員のうち少なくとも1人は、児童と起居を共にします。
医療型障害児入所施設には、「児童自立支援専門員」を配置することとされている。正答:×
児童自立支援専門職員は、児童自立支援施設の職員です。
福祉型☆
福祉型は、あまり試験には出ないようですが、一応。
対象:
- 知的障害児
- 精神に障害のある児童(発達障害を含む)
- 身体に障害のある児童(肢体不自由児・盲児・ろうあ児など)
支援の内容
- 日常生活能力の維持・向上のための訓練
- コミュニケーションの支援
- 食事・排せつ・入浴などの介護
など
主として知的障害のある児童を入所させる施設
- 嘱託医(精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者)
- 児童指導員・保育士(児童4人に1人以上)
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
主として自閉症児を入所させる施設
- 医師(児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者)
- 看護職員(児童20人に1人以上)
- 嘱託医(精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者)
- 児童指導員・保育士(児童4人に1人以上)
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
主として肢体不自由児を入所させる施設
- 看護職員(1人以上)
- 嘱託医(精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者)
- 児童指導員・保育士(児童3.5人に1人以上)
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
主として盲ろうあ児を入所させる施設
- 嘱託医(眼科または耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者)
- 児童指導員・保育士(児童4人に1人以上)
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
上記に加え、心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行う場合
- 心理指導担当職員(大学or大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者)
職業指導を行う場合
- 職業指導員
障害児通所支援
児童福祉法第6条2の2では、「障害児通所支援」として次の4つが挙げられています。
障害児通所支援
- 児童発達支援
- 放課後デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
このうち「児童発達支援」を行う「児童発達支援センター」の配置基準はこちら!
※2024年4月より変更されました。令和6年度後期試験より試験範囲です。変更後の配置基準を載せています。※
児童発達支援センター☆☆
児童発達支援センターは、地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行います。
「医療型」と「福祉型」に分かれていましたが、児童福祉法の改正により、2024年4月からは「児童発達支援センター」に一元化されました。
対象:
- 知的障害児
- 精神に障害のある児童(発達障害を含む)
- 身体に障害のある児童(肢体不自由児・難聴児など)
- 在宅の重症心身障害児
支援の内容
- 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得
- 集団生活への適応のための支援
- 治療
など
児童発達支援センターの職員は
- 嘱託医
- 児童指導員
- 保育士
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合
- 機能訓練担当職員
医療ケア児がいる場合、医療ケアを行う場合
- 看護職員(医療機関と連携する場合はおかなくても可)
肢体不自由のある児童に治療を行う場合
- 医療法に規定する診療所として必要な職員
医療型児童発達支援センターには、心理療法担当職員を配置することとされている。正答:×
医療型児童発達支援センターの対象は主に「肢体不自由児」なので、「心理療法担当職員」ではなく、「理学療法士または作業療法士」が必要です。
心理療法担当職員は、児童心理治療施設に配置されます。
ミニテスト
→うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
※一部解説を訂正しました。(H30.10.10)


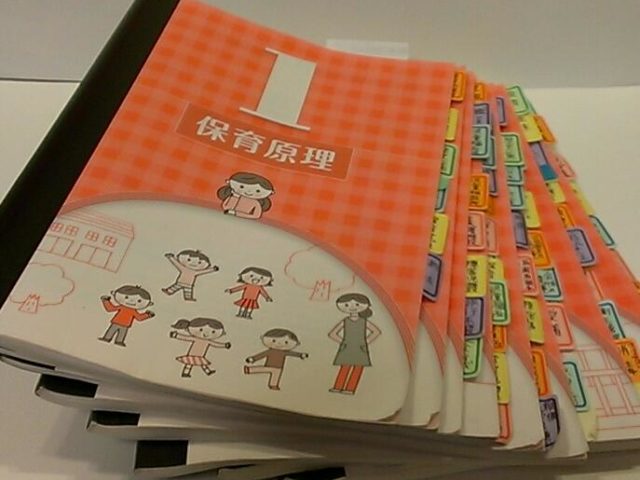


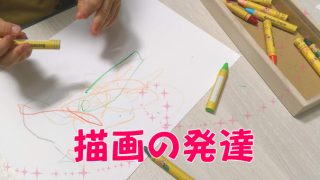






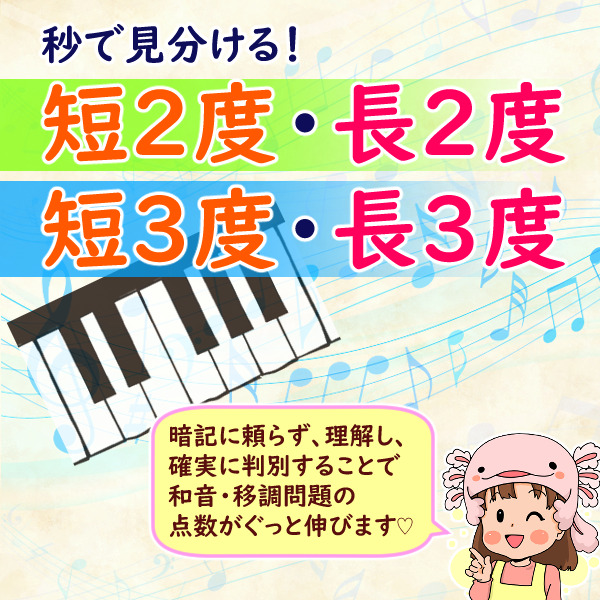
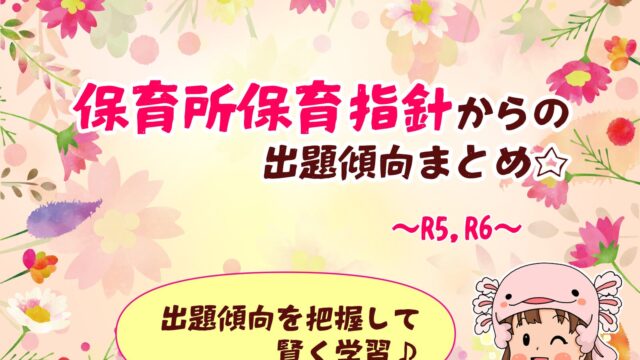



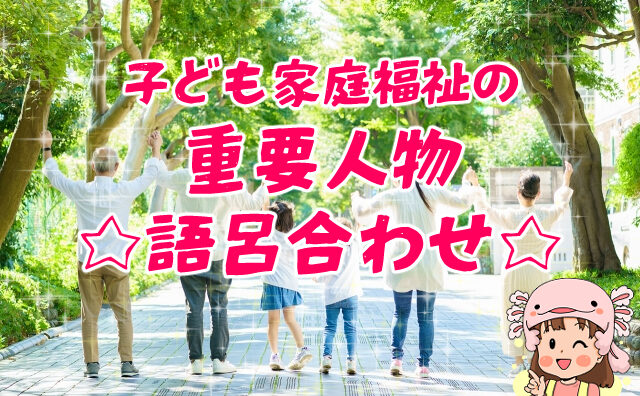
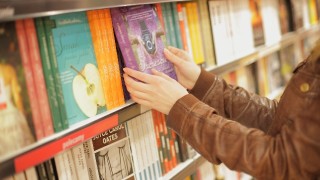
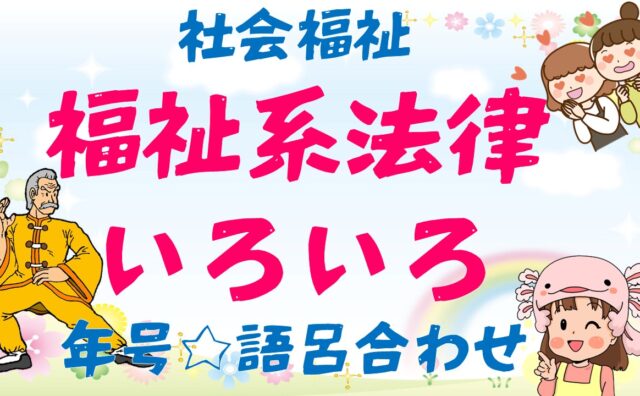
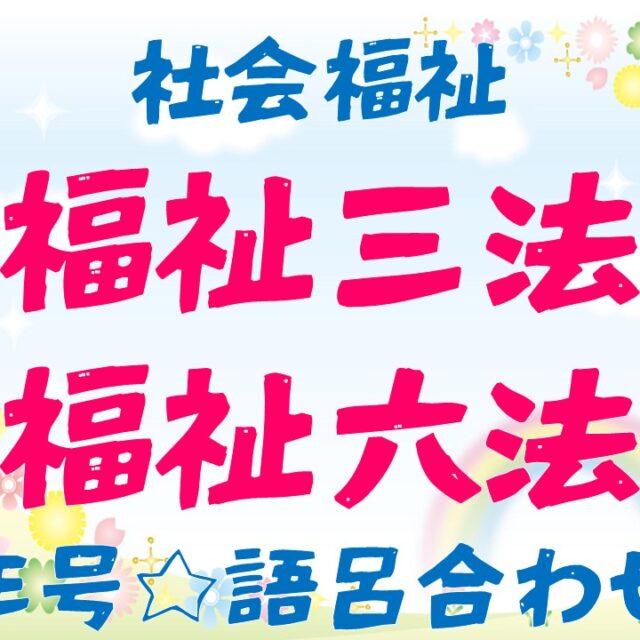
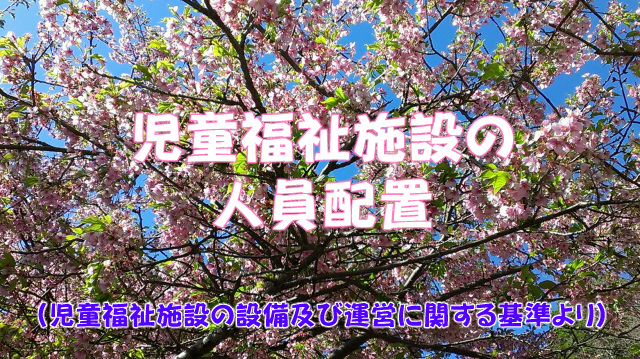

コメント
追い込みの時期にミニテストを作っていただけるのは本当に嬉しいです。
ありがとうございます‼︎
Ikuさん、コメントありがとうございます。
ご覧くださってありがとうございます(●^o^●)
少しでも力になれればとちょこちょこ更新しています。
試験まであと少し!最後まであきらめず頑張ってくださいね❀
うぱみさま
いつもこちらで学ばせて頂きありがとうございます。
質問なのですが、ユーキャンの問題集に以下のものがあり、答えはバツでした。
児童発達支援には、障害児に対する治療も含まれる。
解説に児童発達支援は児童発達支援センター等に通所する事業で治療は含まれない
と書いてあるのですが、医療型では治療もしますよね?
お忙しいとは思いますが、お時間のある時お返事ください。
しむさん、コメントありがとうございます(^^)
医療型児童発達支援センターは、治療も含まれているので、その解説はもやっとしますね(;´Д`)
うぱみさま
またまた、つまずきました(ToT)
助けて下さい❗
ユーキャンの一問一答に
「児童発達支援センターの入所措置は、障害支援区分に基づき行われる」という問いがあり、答え❌
❌はよいのですが、解説が「障害支援区分は、障害の程度を判定する際に用いられる」となってます。
ネットで調べたところ平成26年度児童家庭福祉で出た問題のようですが「福祉教科書 保育士 完全合格テキスト」にも同じ問題が出ていて、解説も
「障害者区分は障害の程度ではなく必要とされる支援の度合いに基づいて決められる」でした。
そもそも「児童発達支援センター」が入所ではなく「通所」施設だから❌って私は思ったのですが、入所することもあるのでしょうか?
五十の手習いさん、コメントありがとうございます!
私も、児童発達支援センターは、通所のみだと思います(>_<) 各社で見解の分かれる問題なんですかね(・_・;)難しいですね。
うぱみ先生ありがとうございました❗
確認できて良かった
もやもやが晴れました
うぱみさま
こんにちは
いよいよ、あと二週間になりドキドキしています。復習も記憶も追い付かない頭の状況にドキドキ…
あのぉ、重症障害児が医療型入所施設に入所のときは、理学療法士、作業療法士と「心理療法担当員」となっておりますが、「心理指導担当員」?
すみません、一度みていただけますか?
私の勘違いでしたら、すみません
くるたんさん、コメントありがとうございます(*^_^*)
心理指導担当職員ですね!細かいところまでありがとうございますm(__)m
訂正しましたので、ご利用ください♪
試験勉強頑張ってくださいね~☆