子ども・子育て支援新制度の中で、たまに出題される事業について。 しっかり違いを理解しておきましょう♡ 
- 子育て短期支援事業
- 子育て援助活動事業
- 一時預かり事業
- 延長保育事業
- 病児保育事業
どれも、子育てママの「助けて!」に応えてくれる事業ですよ♪
子育て短期支援事業
「出産や病気で入院する間、夫は仕事を休めないし、他に子どもを見てくれる人がいない。」「冠婚葬祭や出張で子どもを預けたい」「育児に疲れてちょっと休みたい」などの時などに、一時的に預かってくれます。
「夕方~夜や、休日(日帰り)」「泊り」を選ぶことができます。
「夜間・休日(日帰り)」を「トワイライトステイ」。
「宿泊」を「ショートステイ」といいます。
児童養護施設のほか、母子生活支援施設、乳児院、保育所など保護が適切に行える場所であり、子育て家庭にとって身近な場所で行われます。
親子で利用可能
2024年4月1日の児童福祉法改正により、「保護者が子どもと共に入所・利用が可能」であることが明文化されました。
つまり、子育て短期支援事業は「児童のみの利用」だけでなく、「親子での利用」もできるようになりました。 この場合は、母子生活支援施設などの児童福祉施設が利用できます。
子どもが「希望」して入所することも可能
2024年4月1日の児童福祉法改正により、「入所希望児童支援」ができることが明文化されました。
児童養護施設、保育所、ファミリーホーム等、住民にとって身近で、適切に保護することができる施設を利用できます。
子育て援助活動支援事業
ファミリー・サポート・センター事業ともいいます。
「助けてほしい人」と「力を貸してあげたい人」を結び付ける事業です。 保育園のお迎えに間に合わない!買い物に行く間預かってほしい!という時に、ファミリー・サポート・センターに連絡すると、提供会員の方を紹介してくれます。
- 助けてほしい人→「依頼会員」
- 力を貸してあげたい人→「提供会員」
助けてほしい時もあるけど、手の空いている時には、力を貸したいよ!って人は、依頼会員と提供会員の両方になることもできます(両方会員)。
「資格」は必要なし
提供会員になるには、とくに「保育士」や「看護師」などの資格は必要ありません。 「忙しい時にちょっと見てあげるよ」とおじいちゃん・おばあちゃん、近所の人、ママ友などが、ちょこっと預かってくれることがあると思いますが、そういった方が近くにいない場合に、預かってくれる人を紹介(連絡・調整)してくれる事業です。 ただ提供会員には「資格が必要ない」だけに、事故を防げるだけの資質を確保できているかどうか・・・。過去には死亡事故も起きています。

預かるのはボランティア的な要素が強く(雇用契約ではない)、謝礼を払いますが、安いです。 ベビーシッターよりも時給が安いので、どうしてもお金がないけど預けたい時には便利です。 しかし、雇用契約ではないので、事故が起きた時の保障は期待できません。 H21より病児も預けられるようになりましたが、なるべくなら病児は看護師が看てくれる「病児保育」(下記参照)を利用した方が・・・と思います。
一時預かり事業
- 家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
- 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
「子育てにかかる保護者の負担を軽減=レスパイト」目的での一時預かりが可能であることが明文化されました。
- 一般型 ・・・保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない(在籍していない)乳幼児が対象。就学前で特定地域型保育事業者を利用していない&保育所への入所が決まるまでの間、定期的に通う場合も対象。
- 余裕活用型 ・・・定員に空きがある保育所、認定こども園、家庭的保育事業所などで実施することができる。
- 幼稚園型Ⅰ ・・・認定こども園・幼稚園に在籍している1号認定の園児(満3歳以上)を対象とした事業。(園児以外の子どもを預かる時は「一般型」として対応)
- 幼稚園型Ⅱ(「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村のみ) ・・・家庭において必要な保育を受けることが困難として市町村に認定された0~2歳児を、幼稚園で預かる事業。
- 訪問型 ・・・児童の家へ訪問して、一時預かりを実施。
幼稚園型、ややこしいですね(・_・;)
平成29年度前期試験 児童家庭福祉 問12 次の文は、一時預かり事業に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。正答:3
- 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児について、保育所等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業であり、乳児は対象とされていない。
- 実施場所は、保育所、認定こども園等であり、幼稚園は除外されている。
- 実施主体は、市町村である。なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
- 一時預かりの対象は、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない幼児である。
- 職員には必ず家庭的保育者が含まれていなければならない。
1は、「乳児は対象とされていない」の部分が明らかに違うとわかりますね。 2,4は、この事業についてしっかり理解しているかを問う問題です。 5は「家庭的保育者」ではなく、「保育士」(幼稚園型は「幼稚園教諭」でも可)ですね。
延長保育事業
保育認定(2号・3号認定)を受けた子が対象です。(延長保育事業「一般型」) 幼稚園に通っている子は1号認定なので、幼稚園の延長保育は「延長保育事業」ではなく、「一時預かり事業」です。 居宅訪問型保育でも延長保育を受けることができます。(延長保育事業「訪問型」)
病児保育事業
- 病児対応型・病後児対応型 ・・・病気で保育所を休まなければならないけれど、保護者の勤務の都合などで家庭で保育できない子を、病院や保育所に敷設された専用スペースや専用施設などで預かる。 子ども10人に対して看護師1名以上、子ども3人に対して保育士1名以上配置
- 体調不良児対応型 ・・・保育所に通っている子で、保育中に体調の悪くなった子を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所の医務室や余裕スペースなどで預かる。 看護師を常時1名以上配置(子ども2人に対し看護師1名)
- 非施設型(訪問型) 保護者の自宅へ訪問し、保育する。 看護師または保育士または家庭的保育者1名に対し、児童1名程度。
R3後 子ども家庭福祉 問 11 次のうち、病児保育事業に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む)であるが、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 →〇
- 事業類型は、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)、送迎対応である。 →〇
- 乳児・幼児が対象であり、小学校に就学している児童は対象にならない。 →×
- 病児対応型及び病後児対応型では、病児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね 10 人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置しなければならない。 →〇
ミニテスト
子育て短期支援事業、子育て援助活動事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業の内容をしっかり理解しているかを問うミニテストです! →うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
当事者意識で考えよう
ごちゃごちゃしてきてしまった人、自分が困った場面を想像して考えるといいですよ。
- お父さんに仕事を5時で上がってもらう。 (これは難しそう)
- 幼稚園の延長保育(一時保育事業)を利用 (延長保育の料金が発生。9時まで預かってもらうのは難しい)
- ファミサポ(子育て援助活動支援事業)を利用。9時ごろまで提供会員の家で預かってもらう。(安いけど)
- 子育て短期支援事業のトワイライトステイを利用 (資格を持った人が、施設で預かってくれて、保育園への送迎もしてくれるので安心)
・・・自分の子が熱を出したら、心配で仕事休んでつきっきりで看たり病院に連れて行ったりが普通だと思いますが、色々な事情のある人もいますからね・・・。どんな制度を利用できるか、考えてみましょう。
- 病児保育を利用 (看護師、保育士が看てくれて安心)
- ファミサポ(子育て援助活動支援事業)を利用。提供会員の家で預かってもらう。 (安いけど、制度上病気の子を預けることもできるけど、体調急変した時に大丈夫?)
- 連絡帳に「元気です」と書いて保育園へ。保育園で熱が出たことにして、病児保育(体調不良児対応型)で預かってもらう。(これはやっちゃだめ)
保育士試験対策+αテスト
子育て短期支援事業、子育て援助活動事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業の内容について、かなり細かいところまでミニテストにしました!

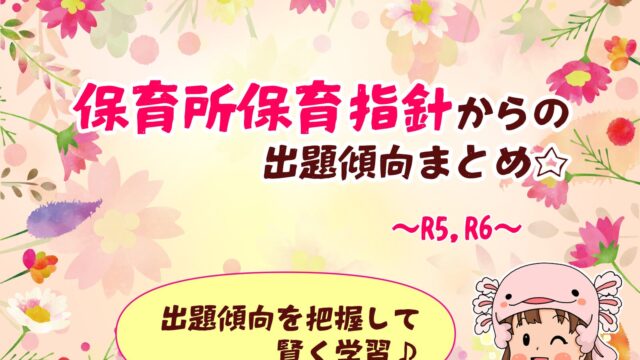





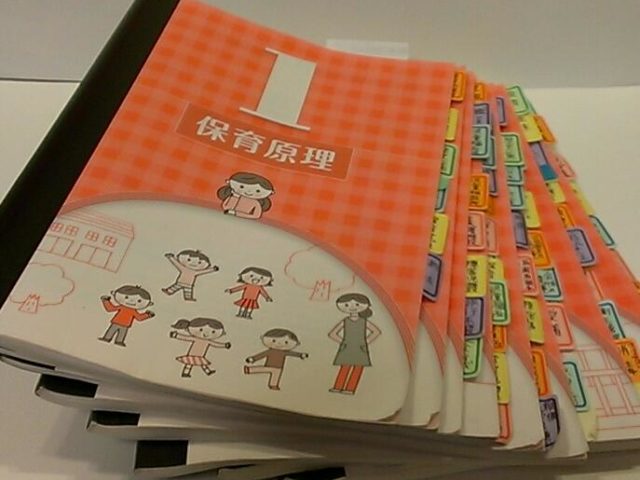
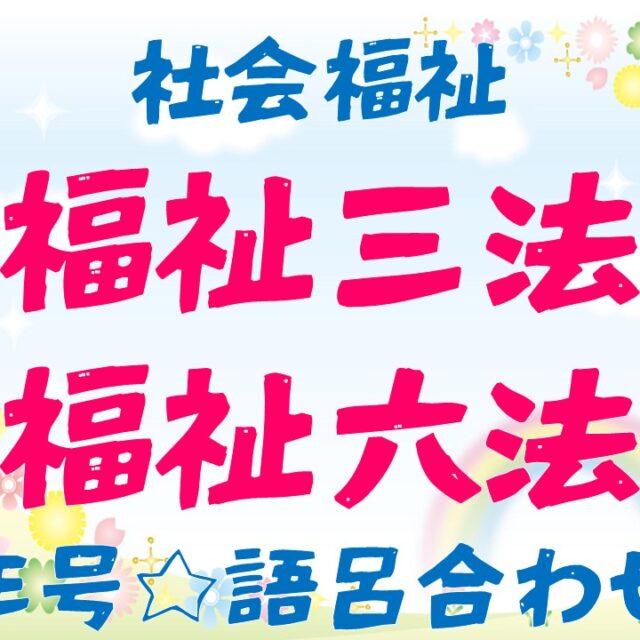
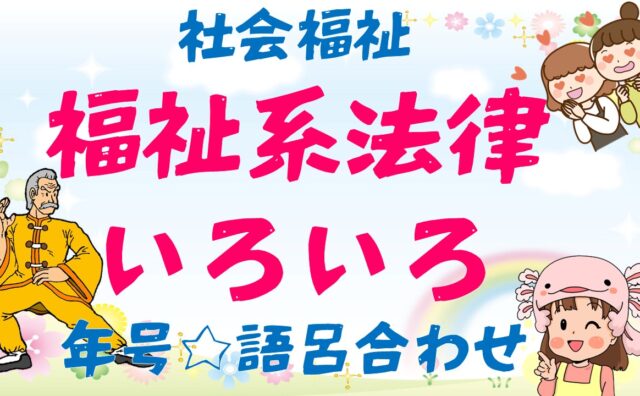
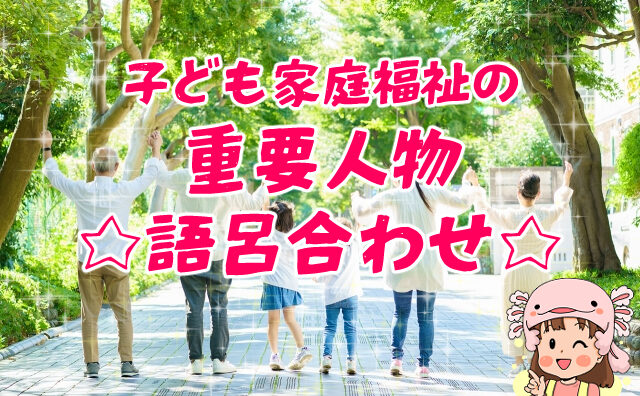

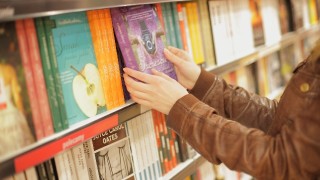





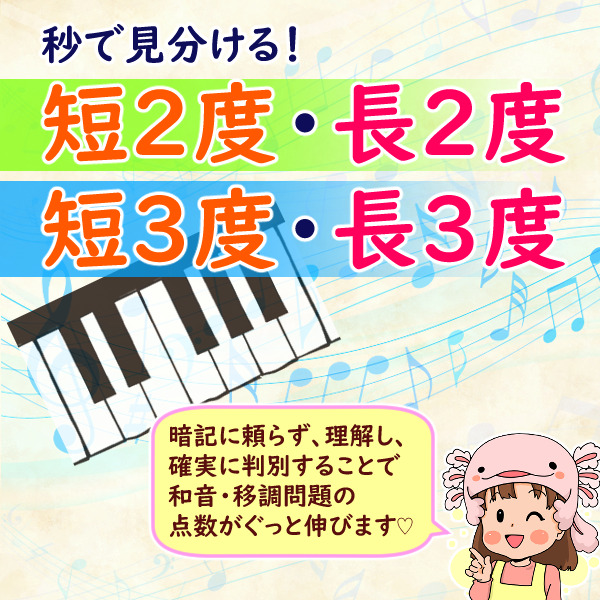

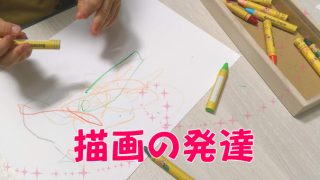



コメント
初受験前に偶然にもうぱみさんのサイトを発見させていただき、
目からうろこが剥がれ落ちまくっています。
痒い所に手が届く、腑に落ちていなかった
保育士試験の言葉にできない難解さを
あの手この手で解きほぐしていただいています。
本当に受験前に出会えてよかったです。
ありがとうございます。今週がんばります。
やまぐちたつこさん、コメントありがとうございます❀
お役に立ててうれしいです!試験頑張ってください♡
このサイト、見つけてびっくりしました。
どこのテキストよりもわかりやすい!!
そして、時々覚え方まで教えてくださって、神様のようです。
「子ども家庭福祉なんて、複雑過ぎてわけわかんない」
と投げていたのですが、少しわかってきました。
このサイト、書籍化されると嬉しいです。本のほうが読みやすいアナログタイプなので、、、
さやかさん、コメントありがとうございます!
分かりやすいと言っていただけて、嬉しいです(*^▽^*)
勉強頑張ってください♪